| 翌朝カールはドアをノックする音で目を覚まし、慌ててドアまで駆け寄ると廊下に声を掛けた。 不自然ではあったが、まだ服を着ていなかった為、そうするより他どうしようもなかったのだ。 廊下側にいたメイドは少々疑問に思いながらも、ドア越しに朝食の用意が出来た事を伝え、カ ールの返事を聞くとそそくさと立ち去った。 カールがほっと一息ついてベッドへ戻ると、丁度サラが目を覚ましムクリと起き上がった。 「おはよう、サラ」 「おはよ。……誰か来てた?」 「朝食が出来たって伝えに来てくれただけだよ」 「……大変!すぐ支度しなくちゃ」 サラは眠気が一気に吹き飛び、ベッドから降りると服を着始めた。 うかが カールも一緒になって服を着ながらサラの様子を伺い、今回は大丈夫だったんだと胸を撫で 下ろしていた。 そんなカールの思いを察したのか、身支度を終えたサラは振り返ると笑顔で腰を押さえてみ せた。 「今日は何とか我慢出来そうよ」 「何とかって……やはり痛いのか?」 「うん。だって……あなたが意地悪ばかりするんだもん」 とが サラは口を尖らせて言ったが、カールは言う程動じなかった。 サラにあんな表情をされては、意地悪したくなるのは当たり前の事。 そうカールは勝手に納得し、嬉しそうににっこりと微笑んでみせた。 ふく その笑顔に疑問を感じたサラは頬を膨らませ、プイとそっぽを向いた。 「どうしてああいう事をする時はいつも強引なのかしら?」 「君の方こそ、どうしていつも従順になるんだい?」 カールは笑顔のまま聞き返したが、サラはその問いに答えられなかった。 かな サラがカールの力に敵うはずがないとわかっていながらそういう質問をするのは、ハッキリ言 って意地悪以外の何物でもない。 ふ サラは腑に落ちないといった表情で黙ってカールを見つめた。 「ごめん、また意地悪してしまったな……」 わ カールは素直に謝ると、お詫びのつもりでサラの頬を優しく撫で始めた。 その手をサラは自分の手と重ね、カールの温もりをじっくり感じてから微笑んだ。 「あなただったら、何されても許しちゃうよ」 「サラ……」 サラの本音を聞き、嬉しくなったカールは思わず彼女を抱きすくめていた。 うず サラは自身が言った言葉に少々照れつつ、カールの胸に顔を埋め幸せそうに目を閉じた。 ほうよう そうして二人はしばらく熱い抱擁を続けていたが、途中でハッと朝食の事を思い出すと顔を見 合わせた。 「あ、朝食……」 「すっかり忘れていたな、急いで行こう」 「うん」 すで カールとサラは小走りでダイニングルームへ向かったが、時既に遅かった様でファーレン達は 先に朝食を食べ始めていた。 ファーレンは遅れて来た二人を思いきり非難の目で見ながら黙々と食べ続けた。 「遅れて申し訳ありません」 「………さっさと席に着け」 「はい」 親子の会話は非常にぎこちなく短かったが、カールは余り気にせずサラを先に座らせ、自分も 静かに席に着いた。 すかさずメイド達が二人の朝食をテーブルに並べて後ろへ下がり、朝から険悪な雰囲気で食 事の時間が始まった。 しかしソフィアだけは相変わらずいつもの調子で、嬉しそうにサラに話し掛けた。 「ねぇねぇ、サラちゃん。昨日はバタバタしてて話す暇が無かったけど、今日はお茶でも飲み ながらゆっくりお話しましょうねv」 「は、はい」 昨日も充分話していたはずではないか、とファーレン以外の全員が思ったが、ソフィアにとって は話し足りなかった様だ。 サラはこれは長話になるなと覚悟しつつ、少し楽しみでもあった。 ソフィアの話はカールに関するものが多く、どれもサラが聞きたい話だったのだ。 やがて静かな朝食の時間が終わると、ソフィアはサラとカールを連れて中庭へ向かった。 中庭には紅茶を飲む為の準備が完璧に整えてあり、ソフィアは二人に椅子を勧めると、いそ いそと紅茶を用意し始めた。 三人分の紅茶を用意し、サラ達の前にカップを置いたソフィアは笑顔で席に着いた。 「あのね、サラちゃん。正直に答えてほしいんだけど……」 「……は、はい、何でしょうか?」 ひ 「この子のどこに惹かれて好きになったの?」 「え……?」 「だからぁ、カールを好きになった理由よ、り・ゆ・うv」 「そ、それは…その……」 サラは顔を真っ赤にしつつ、助けを求める様にカールを見つめた。 や 昨日はこういう質問は止めてほしいと言っていたカールだったが、今日は何故かソフィアを止 めようとはしなかった。 実はカールも知りたいと思っていた事だったからだ。 サラは逃げ場を失って困り果ててしまい、どう答えようかと必死に思案し始めた。 「えっと……あの………」 「なになに?」 つらぬ 「……どんな苦難にも屈せず、自分の信念を貫き通す所……だと思います」 「ん〜、サラちゃんの気持ちよくわかるわ〜。私もそうだったからv」 ひょう そう言ってソフィアは若い頃を思い出してしみじみと頷き、彼女とは対照的にカールは少々拍 し 子抜けしてしょんぼりしていた。 彼は全く別の答えを期待していた様だ。 のが 早く今の話題から逃れたいサラはソフィアの反応を見、それとなく彼女の話題にすり替える事 にした。 「お母様はお父様とどこで知り合ったんですか?」 「うふふv 知りたい?」 「え、ええ、もちろんです」 「私達はねぇ、職場結婚なのよv」 「え?職場…?」 ファーレンは元帝国軍人…… かし という事はソフィアも軍人だったのだろうか、とサラが首を傾げていると、その疑問を察したカー ルが補足説明を入れた。 「母さんは軍医だったんだ」 「へぇ〜、それで職場結婚なのね」 サラは軍人と軍医の組み合わせに心ときめかせ、ファーレンとソフィアをカールと自分に置き か 換えてうっとりした。 「…で、プロポーズはどちらからなんですか?」 「やだ、もぉ〜。そんなの、あの人からに決まってるわよ〜」 「お父様からですか。当然の様な、意外の様な……」 「やっぱりそう思う?あの時は私もさすがにビックリしちゃったわ〜、余りにも突然だったから」 「い、いきなり告白されたんですか?」 「いきなりって言うか……実は私ね、若い頃結構もてていたんだけど、決まった方とはお付合 いしてなかったの。あの人とは他の兵士さん達と一緒で、基地の医務室で何度か会った事が いだ ある程度で……。だから顔見知りではあっても、好意を抱いてくれてるなんて夢にも思ってな かったのよ。なのにあの人ったら、突然プロポーズしてきてね〜。私最初は何の事やらさっぱ りで、プロポーズだって気づくのに何ヶ月も掛かっちゃったの〜」 「へ、へぇ、そうだったんですか…」 確かにこののんびりさでは、気づくのにそれくらい掛かってしまうだろう。 ファーレンの苦労が伺える話であった。 サラとカールが顔を見合わせ苦笑していると、突然三人の元へメイドが駆け寄って来た。 「奥様、お客様がいらしております」 「あら、こんなに朝早くに誰かしら?」 「そ、それが……」 よど メイドはどういう訳か言い淀んでハッキリ答えず、その間に客人と思われる数人の女性達がす ごいスピードで中庭へやって来た。 いか 美しいドレスを着ており、如何にもお嬢様といった印象を受ける女性を筆頭に、如何にもメイド といった服装の女性達が後に従っていた。 「お久し振りです、ソフィア様」 「あらまぁ、シルヴィアさんじゃないの〜。久し振りねぇ」 すそ シルヴィアと呼ばれた女性はソフィアに挨拶した後すぐにカールの方を向き、ドレスの裾を持ち ゆうが 上げ優雅に一礼してみせた。 「お久し振りですわ、カール様」 「…あ、ああ、久し振りだね、シルヴィア。元気そうで何よりだ」 カールは一瞬誰だか思い出せなかったが、ソフィアが名前を呼んでくれたお陰できちんと思い 出し挨拶を返した。 いいなずけ 彼女はカールの許嫁だった女性、シルヴィア・マティルナ・フェーレンバッハ。 帝国屈指の名門貴族、フェーレンバッハ家のご令嬢である。 うる せま シルヴィアは一通り挨拶を済ませると、いきなりカールの手を握り潤んだ瞳で迫った。 わたくし 「カール様、どうして突然婚約を解消なさったんですか?せめて事前に私に相談して頂きたか ったですわ」 「す、すまない。色々あって連絡をする暇が無かったんだ」 「お忙しいのはわかりますけど、解消した理由だけでもおっしゃって下されば、こうしてわざわ ざ参りませんでしたのに……」 「そ、それは申し訳ない事をしてしまったね。でも丁度良かった、解消の理由なら今言うよ」 あさって そう言ってカールはサラを呼ぼうとしたが、それよりも早くシルヴィアは明後日の方向に向かっ て一人で話し始めた。 「いいえ、理由は聞かなくてもわかっております。軍人であるあなたはいつ戦場で命を落とす のかわからない身……。私を悲しませない様にわざと婚約を解消したのですね!なんてお優 しいカール様v シルヴィアは幸せ者でございますvv」 「シ、シルヴィア?」 「あぁ、それ以上はおっしゃらないで下さい!わかっています、私と再び婚約したいのですね。 平和な時代になったのですから、そう思われるのは当然です。大丈夫、私の方の準備は整っ あ ております。今すぐにでも式を挙げましょう!」 「い、いや、そうじゃなくて……私の話を聞いてくれないか、シルヴィア?」 「はい、何でしょう?」 ようやくシルヴィアが落ち着いてくれたので、カールは傍観者になっていたサラをそっと前に押 し出した。 けげん シルヴィアはカールの行動の意味が理解出来ず、怪訝そうな顔で首を傾げた。 「カール様、そちらの方はどなたですの?」 ひと 「彼女はサラ・クローゼ。今、私がお付合いしている女性だ」 「………………は!?お、お付合い…?」 「ああ、行く行くは結婚しようと思っている。だから君との婚約を解消したんだよ」 カールの言葉によってシルヴィアの目の前は真っ白になり、ふらふらと力無く倒れ込んだ。 ささ すかさず付き従っていたメイド達がシルヴィアを支え、傍の椅子に座らせた。 黙ってその様子を見ていたサラはカールの腕をつつき、小声で話し始めた。 「……ね、ねぇ、唐突すぎたんじゃない?」 「そうかなぁ…。三年も前に解消したから大丈夫だと思ったんだが……」 カールとサラはシルヴィアの意識が戻るのを待ち、先程言った事をもう一度ハッキリ伝えた。 うつ シルヴィアは虚ろな目をして聞いていたが、サラの姿が視界に入った途端目つきがガラッと変 わり、勢い良く椅子から立ち上がった。 わきま 「あなたみたいな方がカール様とお付合いしているなんて……身の程を弁えてほしいですわ ちゃくなん ね!シュバルツ家の嫡男の嫁になるという事が如何に大変な事であるか、あなたはご存知 なのかしら?」 「は、はぁ…」 ふさわ 「まぁ、よろしいですわ。あなたがカール様に相応しいかどうか、私が判断させて頂きます!そ ういう訳でソフィア様、しばらくお世話になりますわ」 シルヴィアは一人で勝手に話を進めると、メイド達を引き連れて家の中へ入って行った。 「サラちゃん、大変な思いをさせてごめんね」 いつの間にか紅茶を飲み直していたソフィアは申し訳なさそうに謝ったが、顔はいつもの笑顔 のままだったので余り説得力が無かった。 そんなゴタゴタがあったお陰で、ソフィアから解放されたカールとサラはリビングへ向かい、仲 良くコーヒーを飲みながらたあいのない話を始めた。 「シルヴィアさん、相当あなたに入れ込んでるねぇ」 「…みたいだな。しかし今まで二回しか会った事が無いのに、どうしてあれ程先走れるんだろ う…?」 「二回!?許嫁なのに二回しか会った事無かったの?」 まじ 「ああ。小さい頃に一回と、士官学校に入る前に一回。互いの両親を交えて会ったんだ」 「…じゃあ、二人きりでは一度も無いのね。シルヴィアさん、何だかかわいそう……」 「あの頃はまだ幼かったから、結婚なんて深くは考えてなくてさ。てっきり彼女もそうだろうと 思ってたんだが……」 「シルヴィアさんはその二回だけであなたの事が好きになっちゃったって訳ね」 「俺は君以外の女性に好かれても嬉しくないな」 カールが思った事を素直に口に出すと、サラは照れつつも苦笑して首を横に振った。 「カール、そういう事を言うのは私の前だけにしてね。ファンの子が聞いたら悲しむから」 「わかってる。君の前でしか恥ずかしくて言えないよ」 「ふふふ、それもそうね」 二人が楽しそうに笑い合っていると、誰かがリビングのドアをノックし中に入って来た。 さが 「サラさん、ここにいたのね。あちこち捜し回ってしまいましたわ」 「あ、シルヴィアさん。私に何か用?」 「用はありすぎて困る程ですわよ」 リビングにやって来たのはシルヴィアとその取り巻きのメイド達。 シルヴィアはわざとらしくサラの前まで移動し、勝ち誇った様な笑みを浮かべてみせた。 「あなたの事、詳しく調べさせて頂きました。あなたがあのクローゼ博士のご息女だなんて思 いもよりませんでしたわ。でも…確かクローゼ博士の奥様はお体が大変弱く、お子様を生めな い方だったと伺っております。という事は……」 「……………」 「あなた、クローゼ博士の本当の娘ではありませんのね。そんなどこのご出身かわからない ほま とつ 様な方が、誉れ高いシュバルツ家に嫁ぐなんて無理なお話ですわ。ねぇ、皆さん?」 シルヴィアが声を掛けると、背後にいたメイド達は一斉に頷いた。 よそお こわ サラは必死に平静を装っていたが顔は強ばっていた為、カールには彼女の気持ちが手に取る 様に理解出来た。 「………シルヴィア」 「カール様、おわかり頂けましたでしょう?この方はあなたの妻には相応しくありませんわ」 「相応しいとか相応しくないとか、そんな事は我々には関係ない。これ以上彼女を悲しませる たと 様な事を言うのであれば、例え君でも許さない……!」 「そ、そんな…カール様……」 サラの話をすればカールが彼女に失望し、自分の元へ戻って来てくれると信じていたシルヴィ がくぜん アは、まさか怒り出すとは夢にも思わなかったので、愕然として戸惑いの表情を浮かべた。 そうする内にカールは椅子からすっくと立ち上がり、足早に歩くとリビングのドアを開いた。 「出て行ってくれ」 「……え?あ、あの……」 「さぁ、早く」 カールが本気で怒っていると気づいたメイド達は慌ててシルヴィアを引っ張り、ペコペコと何度 も頭を下げながらリビングから出て行った。 のぞ カールはドアをゆっくり閉めると急いでサラの元へ戻り、心配そうに顔を覗き込んだ。 こぼ サラはカールの優しい瞳に見つめられた途端、ぽろっと涙を零し彼に抱きついた。 |
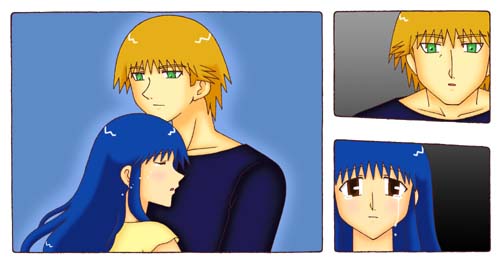 |
| 「ごめんなさい……。ああいう事を言ってくる人は今までもたくさんいたから、もう大丈夫って思 っていたけど……やっぱりまだダメみたい………」 「謝らなくていいんだよ、サラ。人の過去を平気で公言する方がどうかしているんだ」 「でも…シルヴィアさんの気持ちもわかるの……。もしあなたが他の女性と結婚するって言い 出したら……私もきっと同じ事をすると思うわ…。だからシルヴィアさんの事…悪く思わない で……」 ますます 「……君は本当に優しい人だね、益々好きになってしまうな」 つた ふ カールは優しくサラの頬を伝う涙を拭き取り、そっと唇を重ねると強く抱きしめた。 そうしてしばらくの抱擁の後、笑顔を取り戻したサラは照れ臭そうに微笑み、カールの手をぎ ゅっと握った。 「ありがと、もう大丈夫」 「ん、良かった」 カールは安心した様に微笑むと、サラと再び談笑しながらコーヒーを飲み始めた。 やがて正午になり、シルヴィアも参加しての昼食の時間が始まったが、全員が妙な静けさの 中で黙々と食べ続けていた。 ソフィアは珍しく困った様な顔でオロオロと周囲を見回し、その様子を見兼ねたサラは笑顔で 彼女に話し掛けた。 「お母様、後でキッチンをお借りしてもいいですか?」 「キッチン?何か作るの?」 「ええ、お茶の時間に合わせてケーキでも焼こうかと思いまして…」 「まぁ、素敵v 私もお手伝いしてい〜い?」 「はい、よろしくお願いします」 サラ達の話を黙って聞いていたファーレンは、見るからに不機嫌そうにフォークをテーブルに置 くと、ソフィアをジロッと横目で見た。 「ソフィア」 「なぁに?サラちゃんのお手伝いをするだけだからいいでしょう?」 「……本当に手伝いだけなんだな?」 「ええ、もちろん」 しぶしぶ ソフィアがにこやかに笑いながら断言すると、ファーレンは渋々頷き食事を再開した。 サラは何故ファーレンがそんな事を言ったのか理解出来ずに首を傾げたが、カールは理由を 知っていたので黙って食べ続けた。 そうして静かすぎる食事を終え、キッチンへ向かったサラとソフィアはメイド達にも手伝ってもら いつつ、ケーキ作りの準備に取り掛かった。 ファーレンの言葉がずっと気になっていたサラは、材料の分量を量っている間にソフィアにそれ となく尋ねてみる事にした。 「お母様、ちょっとお聞きしたい事があるのですが……」 「ん〜、なぁに?」 「さっきお父様はどうして手伝いだけと念を押したんでしょうか?」 やけど 「あぁ、あれね。あの人ったら私が料理すると怒るの。『指を切る』とか『火傷する』っていう理 由でね。私こう見えても料理は得意だから、何度も大丈夫って言ってるんだけど全然聞いてく れないの〜。ヒドイでしょ?」 「え、ええ、ヒドイですね…」 ファーレンはソフィアの事を相当大事にしているのだろう。 しかし大事にしすぎるのもどうかと思うサラであった。 その頃、カールは子供の頃からお気に入りの場所である二階の大きな窓へ腰掛け、のんびり ぶ と分厚い本を読んでいた。 最近はサラの影響なのか考古学の本を読む様になり、それがとても面白いと気づくと、毎日 あさ 暇を見つけては本を読み漁っていた。 今読んでいる本も考古学の本でサラに借りたもの。 その本からは何となくサラの香りを感じ、それだけでもカールを落ち着かせてくれた。 そうしてカールは夢中になって本を読んでいたが、ふと人の気配に気づくと本から視線を上 たたず げ、静かに佇んでいるシルヴィアの姿を見つけた。 シルヴィアはカールと視線が合った瞬間、慌てた様子で深々と頭を下げた。 「さ、先程は失礼しました……」 「シルヴィア……その言葉はサラに言ってもらえないかな?」 「は、はい…そうですね……」 うなだ 項垂れるシルヴィアを見、カールは自分にも責任があるとペコリと頭を下げた。 「私も少し大人気なかったと反省している、本当に申し訳ない」 「カ、カール様、頭をお上げになって下さい。悪いのは全て私なのですから」 「君一人が悪いんじゃない、きちんと連絡しなかった私も悪いんだ。……だが、一つだけお願 いを聞いてくれないか?」 「一つと言わず、いくつでもお聞きしますわ」 「…サラの両親の話を彼女の前ではしないでくれ。あの人が悲しい顔をすると私も悲しくなる」 その言葉を聞き、ようやくカールのサラへの思いを理解したシルヴィアだったが、長年抱き続 けてきた思いをそう簡単には捨てられないので、苦笑しながら頷いてみせた。 「わかり…ましたわ」 「ありがとう」 カールがにっこり笑って礼を言うと、その笑顔を見たシルヴィアは居たたまれなくなってしま い、彼の前から逃げる様に去って行った。 呆然とシルヴィアを見送ったカールは不思議そうに首を傾げたが、深追いはせずに再び本を 読み始めた。 しばらくしてケーキの甘い匂いがキッチン内を包み込むと、サラは取り分けるのをソフィアとメイ ド達に任せ皆を呼びに行った。 まず最初にカールがダイニングルームに顔を出し、次にたくさんのメイド達が続くと、最後に仏 頂面をしたファーレンがやって来た。 家中を駆け回って帰って来たサラは集まった人々を見回し、シルヴィアがいない事に気づい た。 「ねぇ、カール。シルヴィアさん見なかった?」 「彼女が連れて来たメイドさん達なら来ている様だけど……」 さが カールはサラと同じ様に周囲を見回し、シルヴィアの姿を捜したが見当たらなかった。 「どこへ行ったのかしら…?私、ちょっと捜してくる」 「サラ、ここで待っていれば大丈夫だよ」 カールの制止の声を聞かず、サラはソフィア達に先に食べる様に言ってから、早足でシルヴィ アを捜しに行った。 家の中をしばらく歩き回った後、中庭へとやって来たサラは花園の前に座り込んでいるシルヴ ィアを発見し、急いで駆け寄った。 「シルヴィアさ〜ん!」 「あら、サラさん。何かご用かしら?」 「ケーキが焼けたから、一緒に食べようと思って呼びに来たの」 「……あなたは悩みが無くてよろしいですわね」 そう言ってシルヴィアが立ち上がろうとしない為、サラは隣にしゃがむと一緒になって花を眺め 始めた。 シルヴィアは怪訝そうな目でサラを見つめ、長いため息をついた。 「私が行くまでそうしているつもり?」 「ええ、あなたの所のメイドさん達ももう食べてるよ?」 「あなた変わってますわねぇ。普通、私の様な者はメイドとは飲食を共にしませんのよ」 ため 「でも皆で食べる方がおいしいよ。あなたも多分そう思うはずだから、試しに一度一緒に食べ てみない?」 「……あなたって結構強引な方ですのね」 「結構じゃなくてすごく強引だよ。さぁ、行きましょ」 サラは本当に強引にシルヴィアを引っ張り、二人でダイニングルームを目指した。 サラ達がダイニングルームに入ると、カールとソフィアはすぐに二人の元へ歩み寄った。 「待ってたわよ〜、シルヴィアさん。はい、これサラちゃんが焼いたケーキ。すご〜くおいしい から食べてみてv」 「は、はい」 シルヴィアもソフィアののんびりさには敵わないらしく、差し出されたケーキを素直に受け取る と傍の椅子へ腰掛けた。 その隣にサラもケーキを持って来て座り、キラキラした瞳でシルヴィアを見つめ始めた。 「ご、ご心配なさらなくても食べますわよ!」 た ほおば シルヴィアは熱い視線に堪えかね、慌ててケーキを一口頬張ると、じっくり味わってから驚い た様子でサラを見た。 「…おいしいですわ」 「ほんと!?良かった〜v やっぱり皆で食べるとおいしくなるんだよね〜」 ケーキ自体がおいしかったのだが、サラが皆で食べる方に喜んでいた為、シルヴィアは少々 あき 呆れながら黙々とケーキを食べ続けた。 サラとシルヴィアを心配そうに見ていたメイド達は、二人の様子を見て安心して食べるのを再 開し、それぞれ楽しそうに談笑し始めた。 「あれ、お父様は?」 今度はファーレンの姿が見当たらない事に気づき、サラはキョロキョロしつつ傍に立っているカ ールに声を掛けた。 すると、カールはソフィアと顔を見合わせ肩をくすめてみせた。 「父さんなら、さっさと食べて出て行ってしまったよ」 にぎ 「あの人、賑やかな所は苦手なの。でもケーキはおいしかったって言ってたわv」 「そうですか…。直接感想聞きたかったなぁ……」 がんこ 「ごめんなさいね、頑固な上に照れ屋だから」 「いえ、いいんですよ」 サラはにっこり笑って紅茶を飲み、ケーキをパクパクと食べ始めた。 日が暮れてダイニングルームに集まったサラ達は昼食の時とは打って変わり、賑やかに談笑 しながら夕食を食べ始めた。 わだかま シルヴィアはまだ少々蟠りが残っていたが、いつの間にかサラのペースに乗せられ、ソフィア を交えて女性三人で仲良くおしゃべりをしていた。 いぶか その様子をファーレンは訝しげに眺め、カールは安心した様に微笑み見守っていた。 そうして夕食を終えると、サラとカールはすぐに入浴を済ませ自室へ戻り、チェスなどのゲーム をしながらのんびりと二人だけの時間を楽しんだ。 なな その頃、カールの部屋の斜め下に位置する部屋では、シルヴィアがメイド達に髪を整えさせて いた。 彼女はカール達の後に入浴していた様だ。 と つか メイド達はシルヴィアの長い髪を綺麗に梳かしながら、シュバルツ家に仕えるメイドから聞いた 事を話し出した。 「お嬢様の前にカール様がご入浴さなっていたそうですよ」 どうり が 「まぁ、そうだったの。道理であの方の残り香を感じると思いましたわ」 「そう言えば、お嬢様。聞いた話なのですが、カール様はサラ様とご一緒に入浴しているらし いですよ」 「は…!?い、今何て…?」 「ですから、カール様はサラ様とご一緒に入浴を……」 はれんち 「な、なんて破廉恥な方なの!?そんな事でカール様を誘惑していたのね!?」 さえぎ シルヴィアはメイドの言葉を遮る様に言って立ち上がり、どういう訳か突然ベランダへ出ると、 てす 手摺りにバンッと手を置いた。 カールがそんな事でサラを好きになった訳ではないとわかっていたからだ。 メイド達は心配そうにシルヴィアの傍へ行くと、恐る恐る声を掛けた。 「お嬢様……もうカール様の事は諦めた方がいいのではないですか?」 「……わかっていますわ、あの二人が深く愛し合っている事ぐらい。でも……そんなに簡単に 諦めるなんて………」 「……………」 その場にいた全員がシルヴィアにつられて沈んでいると、不意にどこからか歌声が聞こえてき たので、メイド達はキョロキョロと周囲を見回した。 いち早く歌声の主を見つけたメイドが斜め上を指差し、急いでシルヴィア達に報告した。 「あそこ、サラ様が歌っておられます」 「しっ!静かになさい!」 かが シルヴィアは慌ててメイド達を屈ませると、こっそりとサラの様子を伺った。 サラはシルヴィア達に気づいた風もなく、ベランダの手摺りにもたれながら楽しそうに歌を歌い 続けていた。 「美しい歌声ですねぇ…」 「ほんと……サラ様って歌がお上手なのね……」 ほ メイド達はうっとりとした表情でサラの歌声に聞き惚れつつ、コソコソと感想を述べた。 「あ、カール様……」 何の前触れもなく、唐突にカールの姿が視界に入った為、シルヴィアとメイド達は見られてい ひそ る訳でもないのに物陰に身を潜ませた。 カールはこっそりと物音一つ立てずにサラの背後へ行き、歌が終わるのを合図に彼女を後ろ から抱きしめた。 カールの行動に一番驚いたのは当然サラだったが、シルヴィア達もそれと同等の驚きを味わ っていた。 「ビ、ビックリした〜。驚かさないでよ、もぉ〜」 こどう サラは早くなった鼓動を落ち着かせようと胸元をさすり、その様子を嬉しそうに見ていたカール は、彼女の首筋に顔を埋め口づけを始めた。 先程の驚きの為に動揺していたサラは抵抗するのをつい忘れてしまい、顔を真っ赤にしなが らカールにされるがままになっていた。 そんな二人を観察していたシルヴィアとメイド達はドキドキして見ていられなくなり、見つからな そっけつ おちい い内に部屋へ戻ろうと即決したが、今動けば気づかれると動くに動けない状態に陥った。 「……ん……待って、カール」 のが ようやく口を開く事が出来たサラは、すんなりとカールの手から逃れると手摺りにもたれ掛かっ た。 カールもサラの隣に一緒にもたれ掛かり、笑顔で彼女に話し始めた。 「今朝母さんが聞いた、俺を好きになった理由をちゃんと教えてくれないか?」 「……え?お母様に言った通りなんだけど…?」 「あれは取って付けた様な理由だろ?君の本心ではない」 「……昨日も言ったけど、気が付いたら好きになってたから、どこでどう好きになったのかよく わからないの。でもね……」 サラは途中で言葉を切ると夜空を見上げ、大きく伸びをしてからカールに微笑みかけた。 「よく考えてみたら、私も一目惚れかもしれない」 「君も…?」 か 「うん。あの時あなたとは一言も言葉を交わさなかったのに、何故かあなたの姿が心に焼き付 いてしまったの。そんな事初めてだったから最初は戸惑ってたんだけど、今思えばそれがあ なたへの恋心の始まりだったのかなぁ……なんてね」 「じゃあ、俺と全く同じだった訳だ」 やす 「ふふふ、そうねv けど、あなたを好きになった最大の理由はきっと……一緒にいると安らぐ からだと思う」 そう言うなり、サラはカールに抱きつき彼の胸に顔を埋めた。 ひと 「……こうしてあなたの温もりに包まれると、私は独りじゃないって実感出来て……心から安 らげるの」 「……そうだね、君は独りじゃない。俺も君の温もりで安らげるから、きっと俺達は二人で一つ なんだよ」 「カール……」 二人は互いの瞳を見つめると、ゆっくりと顔を近づけていった。 まさ そうして正に二人の唇が触れ合おうとした瞬間、突然大きな音を立てて何かが落ちた。 くし シルヴィアの傍にいたメイドが持っていた櫛を落としてしまった様だ。 「あ、あなた何をやっているの!?二人に気づかれてしまうでしょう!?」 「……もう気づかれてますよ、お嬢様」 「え!?」 シルヴィアが慌てて振り返ると、顔を真っ赤にしたサラが彼女達を見下ろしていた。 「シルヴィアさん達、いつからそこにいたの?」 「さ、さっき出て来たばかりですわ。な、何も見ていませんわよ!?」 「お嬢様、そんな風におっしゃるとバレバレですよ?」 「うるさいわね!とにかく私達は何も見ておりません。では、おやすみなさい!」 言うだけ言ってシルヴィアはとっとと部屋に戻ってしまい、その後をメイド達がそそくさと追っ た。 「う〜ん、見られてたみたいね」 「どの部屋を使ってもいいとは言っていたけど、こんなに近いなんて思わなかったな」 「……明日顔合わすの…恥ずかしいな………」 「やはりベランダはまずかったか……」 サラとカールは思わず顔を見合わせると、肩をすくめつつ部屋へ戻った。 部屋に入るなりサラはすぐベッドへ横になり、カールは窓をしっかり閉めてから彼女の隣に寝 転んだ。 すると、サラはカールに体をピタッと密着させ、嬉しそうに微笑んでみせた。 かい 「あなたの家に来てから、お互いの事がたくさんわかったねv それだけでも、ここに来た甲斐 があったって思う」 「俺も同感だ。無理に来てもらってずっと悪いなって思ってたけど、一緒に来て正解だったよ」 「お父様とお母様に感謝しなくちゃ」 「そうだね」 カールはにっこり笑って頷き、サラの頬を優しく撫でながら唇を重ねた。 から サラはカールの濃厚な口づけを受ける為、彼の首に手を回してしっかりと抱きつき、激しく絡ん でくる舌を素直に受け入れた。 甘く長い口づけが終わると、二人は互いの瞳を見つめ幸せそうに微笑み合った。 「おやすみ」 「おやすみなさい」 ひたい つ 二人は額に軽く口づけし合ってから、身を寄せ合い眠りに就いた。 ●あとがき● とうとう許嫁なる人物・シルヴィアが登場しました。 カールっていいトコの息子さんですから、許嫁くらいいるだろうと思ったのですが… 私ったらチャレンジャーですねv(笑) しかしカールとサラの絆は固く、間に全く入り込めないというのが何とも… そこが一番主張したい所だったと言ったら、シルヴィアがかわいそうですね。 カールの一人称の移り変わりはどうでしたでしょうか? ウケを狙った訳ではありませんが、相手によって見事に変える所が如何にもカールらしい。 シルヴィアとは昔からただの知り合いとして接していた様です。 シルヴィアには色々と頑張ってもらおうかなぁと考えていましたが、本人は既に諦めの色が濃 くなっています。 やはり三角関係は私には向いていないシチュエーション。 でもシルヴィアにはいい女として最後まで頑張って頂く予定ですv ●次回予告● 来た時も唐突でしたが、帰る時も唐突。 シルヴィアはカールとサラの仲を認め、笑顔で帰って行きました。 そしてカール達はビュルツブルク町へ買い物に出掛け、そこであるものを買い求めます。 二人にとって誓いの証となるその『あるもの』とは一体何なのか? 第五十六話 「シュバルツ家〜三日目〜」 サラ、どれでも好きなのを選んでくれ |